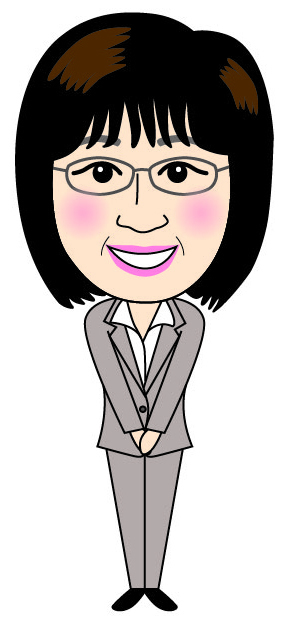障害認定の地域差に関する調査結果について
障害基礎年金の審査は、日本年金機構の都道府県事務センター行われていますが、都道府県によって不支給と決定される割合(不支給割合)に差があることから、実態調査が行われました。
不支給割合は、最も高い大分県で24.4%、最も低い栃木県で4.0%であり、6.1倍もの差が認められます。
全体の支給申請のうち精神障害・知的障害の方からの申請が66.9%を占めており、これらの障害に係る不支給割合が、この地域差に大きく影響していることがわかりました。
その原因は、「日常生活能力の程度」を評価する5段階の運用にあり、地域によって異なる運用をされていることが明らかになりました。
この5段階評価は
(1)精神障害(知的障害)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3)精神障害(知的障害)を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)精神障害(知的障害)を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5)精神障害(知的障害)を認め、みのまわりのこともほとんどできないため、常時援助が必要である。
となっており、不支給割合の低い県においては(2)相当を障害基礎年金を支給する目安としている一方、不支給割合の高い県においては(3)相当を支給の目安としていました。
これを踏まえて、厚生労働省と日本年金機構は、精神・知的障害の等級判定のあり方について平成27年2月以降に専門家による会合を開催し検討するとのことです。
障害基礎年金の審査に地域差があることは、障害年金に関わる社労士、障害者団体の方等、みんなが感じていたことです。やっとその実態と原因がわかったのですが、統一された「認定基準」があるにもかかわらず、その運用については地域任せになっていたとは、お粗末なことです。
審査は、もちろん上の5段階のみで等級判定されるわけではありませんが、目安のひとつとなっています。厳しい審査の方に、統一されるのではないかという心配が頭をよぎります。
サイドメニュー
- 障害年金ガイド
- 障害別のポイント
- 事務所紹介